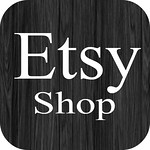Mocenigo Palace Museum, Venice(モチェニゴ博物館、ヴェニス) -2-
7月28日(火)~ 8月18日(火)の間、
KotomiCreations Etsyショップは、夏季休暇で閉店しています。
8月19日(水)より、通常営業に戻ります。
よろしくおねがいします。
今年も、まだいろいろ不便・不自由ではあるものの、例年どおりノルマンディーの夏休み(季節労働?)に出かけられるようになって、とても嬉しい。
世の中の出来事と、ほとんど関与していないノルマンディーの隠者、ペーターおじさんの元で、浮世離れした生活をしていると、なにかとイラッとくる不便・不自由を、しばらくの間は忘れて過ごすことができることと。
しかしその前に、会う人やら、用事やら、庭の世話などで、急に忙しくなってきてしまった。
標本箱の方は、引き続きヴェニスのお屋敷ミュージアムの一つMocenigo Palace Museum(モチェニゴ博物館)のイメージを。

この後の展示室は、18世紀のコスチュームや、
家具などがテーマになっている。
この部屋は、もともとは図書室で、
書籍のキャビネットが残されている。

コスチュームという点では、この部屋が一番充実した部屋で、
18世紀の男性用ウェストコート(ベスト)が、
集中的に展示されている。

刺繍が凝っている。

こういうの、自分でも着たい(笑)。

もう一つの、コスチュームの展示室。
中国、清朝のガウンに近いのは、
18世紀のシノワズリの流行によるものなのかな。
コスチュームの展示といえるのは、以上で終わり。
ちょっとがっかり。

豪華なファブリックと、ヴェネチアグラスの器の展示室。
絵画はAntonio Stomの、
“Arrival of Princess Violante De’Medici in a Square in Verona”。

正面から。
モチェニゴ家を称える、絵画のシリーズの一枚で、
モチェニゴ家の所領下のヴェロナに、
メディチ家公爵夫人を迎える式典が描かれたもの。

このあたりから、もうどの部屋だったのか、
ディティールは解らなくなってきているけれど、
赤・オレンジに金のコンビネーション、
巨大な鏡がいかにもヴェニス的。

19世紀以前の建築に廊下はなくて
(この建物は、17世紀のもの)、
ドアが部屋から部屋へと繋がっている。

肖像画は、モチェニゴ一族を描いたものかと。


この部屋の絵画も、Antonio Stomの、
モチェニゴ家を称える、絵画のシリーズ。
テーブルのガラスの下に展示されているのは、
貴重な13-14世紀のファブリックの断片だそう。
(後で知った。)
この博物館では、こうやって少しずつヴェネチア的なる
ブロケード(絹紋織物)が展示されていたのだけれど、
インテリアに組み込まれてしまっていて、
見て回っている時は、あまり気づいていない。
この部屋なんて、実に見づらくもあるし・・・。
で、ファブリックの展示なんてあったっけ?
って、思うのだった(笑)。

訪れている時は、
シャンデリアやガラス器に意識が向いている。

次の部屋は、コンテンポラリー絵画作品の展示だったので、
あまり興味なくて、天井画の方に注目。

Apotheosis of the Mocenigo Family
(モチェニゴ家の頂点)と題されたもので、
政治的・宗教的権力、知性、正義、
平和、剛毅、美徳などが、
アレゴリー(寓意像)で描かれている。
多彩式のシャンデリアは、18世紀ムラノ製。

この部屋もコンテンポラリー作品の展示だったので、
ちらっと覗いただけ。
多分ビエンナーレの年だったからだと思う。

この部屋の家具は、もともとこのパラッツォに
あったものなのだそう。
(他の部屋の家具は、Museo Correr=
コレッリ博物館からの展示が大半。)

レースの華麗なテーブルクロスは、
レースの産地のブラノ製のもの。

ムラノ製のキノコのテーブル装飾は、
ちょっと微妙だけど(笑)。

最後の写真はシャンデリア。
やはり、ムラノ製のもの。
Mocenigo Palace Museum
(モチェニゴ博物館)
まだまだヴェニスのシリーズは始まったばかりだけれど、
多分・・・もう一度更新はできないまま、
ノルマンディー・ホリデーに突入してしまうことと。
Wifi状況が安定していれば、
ル・シャトーからの更新もある、かも。
Wifiが不安定なら、8月後半にロンドンに戻ってからの更新に。
皆さんもお元気で、
夏とコロナ騒動を乗り切ってくださいね。
*************************
by KotomiCreations
KotomiCreations - Contrado shop item detail
(デジタル・プリント雑貨 - コントラド・アイテム詳細)
Page1, Page2
Labels: 場所