Tassenmuseum Hendrikje(バッグとパース博物館), Amsterdam -2-
春夏コレクションの立ち上げが出来た!!と思ったら、当たり前なんだけど、その納品が連続。 写真のポストプロセスは溜まっているし、そんなこんなで、標本箱の更新も遅れがち。 あー、2週間後のブラッセル(?日本式読み方ではブリュッセルだっけ?)出張までに、先月のアムスの写真が全部仕上がるのかなぁ?実にココロモトナイ。ま、とにかく、できてる写真を標本箱に詰め込んでいくことに。
今回は前回の続きで、Tassenmuseum Hendrikje(バッグとパース博物館)、19世紀以降の展示品を中心に。

展示室の全体像はこんな感じで、布製品の退色を防ぐために、
全体に照明は落とされていて、かなり暗い展示室。

前回の話の最後に出てきたWork Bag(ワーク・バッグ)のディスプレイ・コーナー。
アンドロイド写真にフォトショップでプロセスすると、
オンライン上では、まずまず使える写真になるとわかった。

19世紀に入ると18世紀の頃のように、もっこもこのスカートではなくなったので、
スカートの下にバッグを提げて・・・ということはなくなって、
まさしく「ハンド」バッグになっていく。

外に見えるものなので、自ずと装飾性が増していく。
デリケートなレース編みのもの。

19世紀フランス製。
刺繍というか、レース編みというか、Turkish knots(ターキッシュ・ノット)
と、ミュージアムでは表示されていたけれど、
Turkish Oya(ターキッシュ・オヤ=トルコ・レース)と現在でも呼ばれているものに近い。

刺繍のもの。

19世紀も後半になって、鉄道が普及すると、ご婦人方の活動範囲もずっと広がる。
財布やら、チケットやら、メモノートやら、持ち歩くものも増えて、
より丈夫なバッグが必要になってくる。

ここでやっと、現代人の「ハンドバッグ」のイメージに近いデザインが現れる。
素材も、革製を始めとして、当時開発された、さまざまな新素材が使われた。

べっ甲製のバッグ。

これは確か、べっ甲調のセルロイド製・・・だったと思う。

象牙を模した様々な、プラスチック系の新素材。

オリエンタル調のバッグに使われる。

オペラ用のバッグ。

これは想像だけど、現代よりずっと長いドレスで出歩いているので、
スカートを引っ掛けたり破れたり・・・なんてことも頻繁だったのだと思う。
裁縫キットの付いているバッグもあった。

新素材といえば、スティールがジュエリーにも使われ始めた時代。
バッグにも転用されている。
これはベルトとセットになったベルトポーチ。

スティール・カット・ビーズのバッグ。

手芸の盛んだった19世紀、ビーズ編みのバッグを作ることが流行した。
販売されているパターンを買って、それに準じてビーズをレース糸に通し、
それを編んでいく。
ビーズを通す順を間違えていたら、パターンが狂ってしまう。
絶対に失敗する自信あるわ・・・自分は(笑)。

そのビーズ編みのキット。


中に裏地を張って、上の部分にリングやループを付けて、
チェーンや紐で絞る形に仕上げる。

口金付きのバッグは、チェコやドイツでビーズ織り職人さんが製作したもの。

カーペット状のデザイン。

これも。
余談だけど、私の実の叔母が手芸マニアで、
ビーズ織りバッグにハマっていた、とかいう話を聞いたことがあるけれど、
そのDNAなんだか、ビーズバッグの写真をやたら撮ってしまって、
話がちっとも終わらない。
というわけで、予想外の第3部へ、次回も続きますよ。
Tassenmuseum Hendrikje
(バッグとパース博物館)
Herengracht 573
1017 CD Amsterdam
毎日10:00 a.m. – 17:00 p.m.
入場料: 大人 12.5ユーロ
(祝日閉館等の情報は英文で<このページ>に)
map:
*************************
by KotomiCreations
Labels: 場所
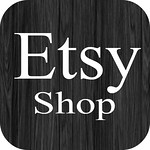




<< Home